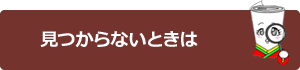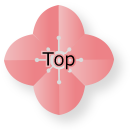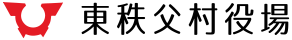本文
国民健康保険の資格確認書・資格情報のお知らせについて
令和6年12月2日以降は『資格確認書』又は『資格情報のお知らせ』を交付します
国の法令改正によって、令和6年12月2日以降、従来の国民健康保険証は新規・再発行されなくなり、マイナ保険証(保険証としての利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。令和7年12月2日以降に東秩父村国民健康保険に加入又は資格情報等に変更があった方にはマイナ保険証の保有状況等により『資格情報のお知らせ』又は『資格確認書』のいずれかを交付します。
※国民健康保険被保険者証は廃止されましたが、東秩父村国民健康保険への加入・喪失手続きは従来どおり必要ですのでご注意ください。
マイナ保険証をお持ちの方(マイナンバーカードを持っており、且つ保険証利用登録済の方)
医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示することで受診することができます。
また、マイナ保険証をお持ちの方には申請なく『資格情報のお知らせ』を交付します。
資格情報のお知らせとは?
マイナ保険証をお持ちの方が、自身の被保険者資格等を簡易に把握できるようにお送りするA4型の通知です。医療機関でマイナ保険証を読み取れなかった時や国民健康保険に切り替えた直後に医療機関にかかる際などにマイナ保険証と一緒に提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。ただし、「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関の受診はできませんのでご注意ください。また、70歳未満の方は有効期限は記載されていません。
マイナ保険証をお持ちでない方
医療機関の窓口等で「資格確認書」を提示して受診します。マイナ保険証を保有してない方には申請なく「資格確認書」を交付します。
資格確認書とは?
資格確認書は従来の国民健康保険被保険者証と同じ大きさのカード型です。
有効期限が翌年7月31日までの資格確認書を交付します。また、マイナ保険証をお持ちでない方には毎年7月中旬に8月から使用できる資格確認書を特定記録で送付いたします。
資格確認書・資格情報のお知らせの交付等について
●新規で国民健康保険に加入される方→マイナ保険証の保有状況に応じて「資格確認書」「資格情報のお知らせ」を交付します。
●マイナ保険証の利用登録を解除申請した方→「資格確認書」を交付します。
●マイナ保険証として使用できるマイナンバーカードを返納した方→資格確認書を交付します。
●令和6年12月2日以降に記載事項の変更があった方(氏名・住所・在留期限更新等の届出をされた方など)→マイナ保険証の保有状況に応じて「資格確認書」「資格情報のお知らせ」を交付します。
●令和6年12月2日以降に70歳になられる方→70歳の誕生月(1日生まれの方は前月)の中旬に、マイナ保険証の保有状況に応じて「資格確認書」「資格情報のお知らせ」を交付します。
これからの医療機関での受診方法について
健康保険証廃止後もマイナ保険証や資格確認書によってこれまで通りの保険診療を受けることができます。また、マイナ保険証による受付ができなかった場合も自己負担10割ではなく、これまで通りの自己負担額で受診することができます。詳しくは下記のチラシをご覧ください。
健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)について
マイナ保険証の登録方法について(マイナンバーカードと健康保険証の紐づけ)
ご自身のスマートフォンや医療機関の顔認証付きカードリーダー、役場の窓口でマイナ保険証の利用登録をすることができます。詳しくは下記のURLをご覧ください。
マイナ保険証の登録方法について<外部リンク>〈外部サイト〉
マイナ保険証では限度額適用認定証等の提示が不要になります
マイナンバーカードの保険証利用登録をされた場合、医療機関等窓口で提示が不要になる証類があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
窓口への提示が不要になる証類について(マイナポータルサイト)<外部リンク>
また、マイナ保険証のメリット等については下記のリンクをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
◎マイナンバーカードの取得は申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。
マイナ保険証における限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の注意点
・マイナ保険証による受付に対応していない医療機関等では利用できません。
・国民健康保険税に滞納がある場合はご利用できない場合があります。
・世帯の中に所得の未申告者がいる場合、限度額の区分を判定できない場合があります。
・直近12ヶ月の入院日数が90日を超える「住民税非課税世帯(区分オ)・低所得者2」の方が、入院時の食事療養費等の減額を更に受ける場合は、改めて役場での申請手続きが必要になります(限度額適用・標準負担額減額認定証の対象者のみ)。